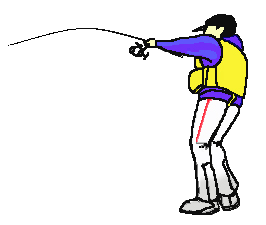
以前は磯竿といえば、道糸を通すガイドが外側に付いている”アウトガイド(外ガイド)”の竿しかありませんでしたが、最近では、飛躍的に技術が進歩し、竿の中に道糸を通すことで、竿自体がガイドの役目を果たす”インナーガイド”タイプの竿があります。 インナーガイド竿はその構造上、ど〜しても穂先が太くなり強度を増す分、重くなりますが、道糸が絡みにくいというメリットは、雨や風や夜間での釣りに、その威力を発揮します。
リールには、スピニングリールとドラムリール(両軸リール)とがあります。
先ずスピニングリールについて解説してみましょう。 スピニングとは「紡績」と訳され、左図のように糸巻きになっているリールです。
昔は、ただラインを巻くことだけだったリールは、技術の進化で巻くことだけでなく、ターゲットの引きに対応する機能...「ドラグ」機能が開発され、釣りに大きな改革をもたらしました。
ソリッド穂先は、低反発で、しなやかに魚を鈎掛かりに持ち込めます。
チューブラー穂先は、高反発でコシが強く、ある程度無理が効いて、対応範囲の広い穂先です。
| ここで紹介するのは主に「上物」をターゲットにした場合のロッド&リールです。 |
(スピニングリールの道糸を巻く部分をスプールといいます。)
スピニングリールは、ワンタッチでスプールを変えることが出来るので、号数や特性の違う道糸を巻いたスプールに素早く交換が出来ます。 もうひとつスプールを用意することで、釣場での状況への対応能力が広がります。
| ロッドとリールの組み合わせ例 |
アウトガイド竿
インナーガイド竿
また、アウトガイド竿は全体的に「細く」「軽い」ところが大きなメリットです。 長い間、インナー竿を愛用している者には、繊細で頼りない感じがしてしまうかも知れませんが、決してそんな事はありません。 ソリッド設計の超高感度な竿先は、余計なテンションを魚に与えることなく、鈎の食い込みを良くし、掛けた魚の引きに応じて竿全体がナチュラルに反応するので、決して魚に隙を与えません。どんなファイターでもじんわりと寄せて浮かせてしまう力強さも兼ね備えていますので、魚とのやり取りを圧倒的有利に導きます。
磯釣りでは、狙うターゲットにより「上物」(表層や中層にいる魚)と「底物」(低層にいる魚)とに大分類され、使用するロッドもそれぞれ「上物竿」・「底物竿」があります。
竿の号数は、だいたい「適合ハリス」と「錘負荷」の号数で決まってきます。
磯釣りは、ターゲット(狙う魚)やフィールド(磯場)によって様々なスタイルがあり、それぞれに対応したロッドがあり、号数がありますので、各メーカーのカタログに記載されている「号数表」を参考にしてください。
竿にテンションが掛かった時...要するにお魚を掛けた時、竿が湾曲する事を”しなる”といいますが、しなりの頂点が先端部分にある竿を「先調子」、竿の中央部分にある竿を「胴調子」といいます。まぁ、感覚的に理解してみてください。
一般的にソリッド穂先の竿は「先調子」で、チューブラー穂先の竿は「胴調子」に設計されています。
道糸の号数(強度)に合わせてドラグを調整しておけば、たとえ、道糸の限界値以上の負荷がかかったとしても、ドラグ調整値を越えた時点からスプールがスリップして自動的に道糸が送り出され、道糸へのダイレクトな負荷を逃がす仕組みになっています。このドラグの導入は、釣り人に圧倒的な主導権を与える結果になり、誰もがその性能に飛びつきました。 糸を巻く技術はこれで頂点を極めたかのように、それから数十年間、ドラグが一世を風靡し、長い間、リールへの改良は施されませんでした。
スプールケース
次に、ドラムリール(両軸リール)ですが、スピニングリールに比べ、巻いた道糸にヨリが入りにくく、道糸の号数(太さ)が大きくなるほど真価を発揮します。 ヨリがあると絡まったり、ヨりが抵抗になったりと、何かとライン・トラブルの原因となってしまいます。 もうひとつのメリットは、ラインを巻き上げる力が強いことにあります。
磯の踊り子
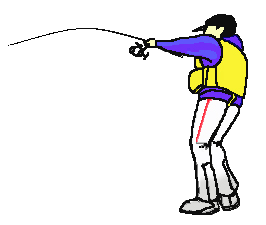
アウトガイド竿の穂先はとてもデリケートですから、取り扱いには十分に注意し、使わない時は必ず専用のキャップでカバーをしましょう。
勿論、インナーガイド竿も同様に穂先を保護しましょう。
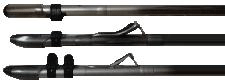
| ↓ リ | ル 番数 |
| →ミチイト号数 |
| スピニングリール糸巻量早見表 |
| ■150m基準 |
| 番数 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10 |
| 1500 | 195 | 130 | 115 | 100 | 80 | ||||||||
| 2000 | 190 | 165 | 150 | 110 | 100 | ||||||||
| 2500 | 200 | 170 | 150 | 120 | 100 | ||||||||
| 3000 | 250 | 200 | 180 | 150 | 120 | ||||||||
| 3500 | 270 | 230 | 200 | 150 | 120 | ||||||||
| 4000 | 350 | 250 | 200 | 150 | |||||||||
| 4500 | 250 | 200 | 170 | 150 | |||||||||
| 5000 | 300 | 250 | 200 | 150 |
あくまで上表は目安にしていただいて、実釣して自らの基準を確立しましょう。 今は各メーカーから機能的かつデザイン性に優れたタックルがたくさん出ていますし、ライン性能も格段に向上しています。 竿もリールもラインも、それぞれ適応範囲が拡がっていて、釣人を益々楽しませてくれてます。
では次に、”ミチイト”とミチイトを巻く”リール”について下表にまとめてみました。
表からも解るように、ミチイトが太くなるほど、リールの番数も大きくなっています。 このリールの番数は、巻けるミチイトの号数と長さによって決められているのです。
| ターゲット | 竿(ロッド) | リール(注2) | ミチイト(注1) |
| クロダイ | チヌ竿0.8〜1.2号 | 2000番 | 1〜2.5号 |
| 口太メジナ | 磯竿1〜2号 | 2500番 | 2〜3.5号 |
| 尾長メジナ | 磯竿1.5〜2.5号 | 3000番 | 3〜5号 |
| 回遊魚(カゴ釣り) | 磯竿3〜5号 | 5000番 | 5〜12号 |
| 回遊魚(泳がせ) | 磯竿5号(または石鯛竿) | 両軸 | 10〜20号 |
◆リールの番数とミチイトの号数
リールにも大小のサイズがありますので、最適なリールを選びましょう。
まず、釣りはその時々の状況に合ったラインを選ぶ事が必要です。そこで重要になってくるのがラインの太さです。 この太さは”号数”により表わされ、数字が大きくなるほど太くなり強度も増します。 同じリールでもラインの号数や巻く長さによって、リールの番数が変わります。ですから、どんなリールを選択するかは、何をターゲットに釣るのか?を考えて、次にミチイトの号数と巻く長さによってリールを選択します。
.gif)
引きの強い大型のターゲットや青物を相手にする釣りでは、ドラムリールのパワーが必要になります。 釣りを組み立てるとき、どんなフィールドで、何をターゲットにするかによって、使用するリールも決まってくるというわけです。







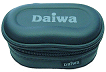

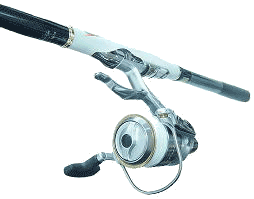


しかし!...どこの誰が思い付いたのか? より釣り人に優位性を与える画期的な機能「ブレーキ」が生みだされました。 しかも”レバー”操作で釣り人が任意にクローズとオープン、ストップとリリースが可能な応用技術。 20世紀最後の釣り革命は、「フカセ」が生み出した究極の「技術」と言っていいでしょう。
それまでの、道具性能に規制された「釣り」は、ドラグ機能とブレーキ機能を併用することにより、釣り人が道具を如何に使うかで無限の可能性を広げ得る「釣り」へと進化したのです。
