オキアミ
(3kg)
アミ(1.5kg)
背鰭 : 15棘13軟条
クロメジナ(オナガグレ)
背鰭 : 14棘14軟条
磯際の攻防が魅力のメジナ釣り
オキナメジナ










沖からの波やウネリが入り組んだ磯へ複雑に寄せては返し、潮流のほかに、離岸流、並岸流、引き波や湧昇流などの複雑な流れを生み出しています。 波の砕けた勢いとともに、岩場に生息するプランクトンや小さな動植物が剥がれ落ち、かくはんされた多くの酸素とともに沖へと流されていく。 流れの中や流れの先でメジナはそのエサを喰うのです。
よく、「メジナは潮の流れを釣れ」といわれるように、潮の流れを読むことがとても重要なポイントになってきます。
では、そんな複雑な潮をどう読めばいいのでしょうか? 第一に目安になるのがサラシです。 沖からの波やウネリが磯場で砕けて白い気泡となって押し返されて出来るサラシ。 このサラシの流れをよく観察することです。 また、エサを撒いてサラシに乗せてみると、より効果的に潮の動きが解るはずです。
さて、潮の流れが解ったら、次は撒き餌のポイントをどこにするかです。 撒き餌をやみくもに撒いても意味はありませんし、広範囲に撒いてもメジナが散ってしまいます。 できる限り流れが生み出されるあたりに撒くといいでしょう。 たとえそのポイントを多少外れて撒いたとしても、必ず一所へ流されていきます。 必ずそこにメジナは寄ってくるはずです。 撒き餌こそ最も重要なテクニックなのです。
次に、仕掛けの投入です。 鍼に付けた”差し餌”を喰ってくれないと釣れないわけですから、如何に差し餌を喰わすかということになります。 先ず潮の流れの手前から撒き餌をサラシの流れに乗せてエサの存在を魚にアピールしましょう。
撒き餌が効いてきたところで、いよいよ差し餌(仕掛け)を投入します。 ここでのポイントは、撒いた撒き餌と差し餌(付け餌)が海中の流れの中で、同調するように仕掛けを投入していきます。 差し餌を撒き餌でカモフラージュさせるようイメージするのがコツです。
ワンポイント・・・撒き餌の主流は”アミ”と”オキアミ”です。 アミやオキアミだけでも充分ですが、より魚を寄せるのに効果的なのが”配合餌”(右図)です。 これを混ぜたものが”撒き餌”となり、専用の柄杓で撒きます。 また、配合餌を混ぜることで、アミやオキアミがまとまり、狙ったポイントに撒き易くなります。
魚を寄せるのに撒き餌は欠かせませんが、魚が満腹になるほど撒き過ぎると返って逆効果になりますので、そこそこの量を定期的に撒いて、魚を寄せられれば、数釣りも可能になります。 また、撒き餌を上手く活用すれば、悩ましいエサ取りの対策としても有効な使い方が出来ます。
ワンポイント・・・「潮の流れ」は、潮汐や打ち寄せる波の強さと方向、風などで敏感に影響され、時々刻々と変わりますので、潮の流れを見極められるよう、常に海の状態をチェックしましょう。 また、潮には上潮、底潮、二枚潮など、複雑な流れもあります。 単に潮の流れを読むだけでなく、その時、メジナはどこにいるかをも読めるようになると、釣りが組み立て易いでしょう。
ワンポイント・・・メジナは”サラシを釣れ”と言う人もいますが、”メジナはサラシを嫌う”という人もいます。 さて、これをどう解釈すればいいのでしょうか? メジナにとってサラシというのは、打ち寄せる波の力で岩場から剥がれ落ちたプランクトンや小さな動植物を豊富に含んだ餌場なのです。 本来、メジナはこのようにして餌を捕食し、磯場を生息域にしています。 また、メジナはとても賢く、しかも警戒心の強い魚なのです。 釣り人が仕掛ける不自然な差し餌を素直には喰ってはくれません。 その不自然な仕掛けを誤魔化してくれるのが”サラシ”とも言えるでしょう。 サラシの効果は充分に活用すべきということです。
■撒き餌・・・最近、撒き餌の”禁止”や”制限”ということをよく耳にします。 釣り人が撒いた大量の餌が、自然浄化に追いつけず海底に蓄積し、自然環境を壊しているためということです。 たまに磯場で見掛けますが、日に6kg~9kgものオキアミを撒いている人がいますが、ちょっと撒き過ぎですね。 日の出から日没までの丸1日にせいぜい4kgもあれば充分です。 撒き餌の撒き過ぎには注意しましょう。
市販の差し餌



磯の踊り子
◆メイン・ターゲット
ウキフカセで狙うターゲットに”メジナ”がいます。
メジナには、写真のとおり大きく分けて3種類があり、それぞれ”メジナ”の名称が付きますが、3種類ともまったく別の種類なのです。
特にメジナ狙いの釣り人たちにとって、 ①強い引きのスリリングなやり取り ②そのスタイル ③食して美味 の三拍子揃っている”尾長メジナ(別名:クロメジナ)”に人気が集中し、釣りのメインターゲットとなっています。




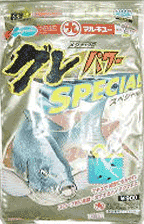
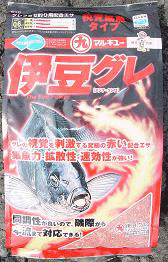


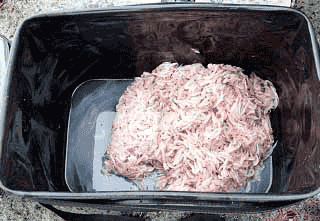


①解凍したオキアミ
②配合餌を適量足す
注)オキアミと配合餌の割合が重要(目安5:5)
混ぜる際には水分調整が重要であり、パサパサ過ぎず
ベチャベチャにならないように。
柄杓で撒きやすいぐらいがベスト。
③よく混ぜる
③よく混ぜる





専用のエサケースの活用も有効です。

磯際でふ化したメジナの稚魚は、幾多の危険や食物連鎖の危機を乗り越えると2年くらいで成魚になります。 成魚といってもまだ小さく、磯際でたくさんの仲間たちと群れを成して過ごします。
小さくて若いころのメジナは活性も高く、磯際のエサ取り集団と化しています。
磯で生まれて、磯で育ち、磯はメジナの棲家であり、特に、起伏に富んだ沈み根や海溝、えぐれ根、ハエ根などをよく好み、動物性プランクトンや小さな魚などの生き物、また、冬場は磯に付いた海苔などを食べています。 単体での行動より、群れでいることが多く、成長するほど好奇心も警戒心も強くなってきます。 昼間の明るいうちは全然釣れなかったのに、夕方になったら急に釣れだした。 というように、昼間は沖や静かなところへ出かけて行き、暗くなってくると棲家に戻ってくる習性があります。
